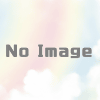【本】「叱らない」が子どもを苦しめる
最近私が気になっていたことと重なる記述の多かった本。
『「叱らない」が子どもを苦しめる』

著者は藪下遊氏,髙坂康雅氏。
教育現場,特に小学生を多く相手する身として学びになる内容が多かった。
打たれ弱い子が増えたなと感覚的に思ってはいたものが,単に私の偏った見方ではなかったこと,そしてその正体が何であるか腑に落ちる内容でした。
↓目次。



>現代の世の中には「自由にさせてあげた方が良い」「叱るのは可哀想」という風潮があることは承知していますが、適切に叱られる、止められる、諫められることによってもたらされる「子どものこころの成熟」も理解しておいてほしいと切に願います。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
書籍では『世界からの押し返し』という表現が繰り返し用いられていたが,『思い通りにならない経験』を積んできていない子の割合が増えてきたのではないか……と私も感じていたもの。
大人が『成功体験』といった耳障りの良い響きにとらわれているのではないかと思うこともある。
>親が「思い通りにならない環境」として立ちはだかると同時に「その不快感を受けとめる」という「一人二役」をしやすいのは、小学校低学年くらいまでなんです。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
これは育児にかかわるものごとに限らないのだけれど,他者を不快にさせるのを避ける世の中になり過ぎているなと感じている。
他のプラス要素が無いのであれば不快は避けることを求められるのだけれど,こと人の成長に関しては避けて通れない不快は確実に存在するだろう。
>私が危惧するのは「ネガティブな自分を認められない」という状態になると、こうした「学び」の基本的な過程自体が生じなくなるということです。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
ネガティブな自身と向きあうことは欠かせないし,それも自身の一部であると受け入れるのも欠かせない。
ここから目を背け続けたりだとか,これに直面するたび同情をひく仕草で解決するような『成功体験』を積み続けて大人になってゆく人もちょくちょく見かけるもの。
>このように考えると、反抗期が生じない理由も明らかです。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
これは反抗期に関する内容で,人によってはショッキングかもしれないので実際に書籍で確認してほしい。
私は反抗期の捉え方に腹落ちした。
>その「不快」がどういったしくみで生じているのかを考えて接することが重要であり、「不快」だから不快にした人が悪いとか、「不快」を除かねばならないというわけではないはずです。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
私も教育現場の人間なので,子どもたちに『不快』を与えることは間違いなくたくさんあるだろう。
自分にとっての快不快をそのまま行為者の善悪と捉える向きもよく見かけるようになったし,改めてこのあたりの認識が広く浸透してほしい。
>彼らが環境と「調和するつもりがあるけど、調和しづらい」のであれば、周囲の大人は彼らの特徴をきちんと把握し、困難を軽減し、その環境にいやすくするための努力を最大限していくことが重要になります。ですが、彼らが環境と「調和するつもりがない」としたらどうでしょうか?
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
ツラい話題も冷静に。
>個性とは「他の人と同じことをしていたとしても滲み出てきてしまうもの」なんです。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
これは本当にそう。
喋りもそうだし,仕草もそうだし,文体もそう。
>本項では、他責的なスタイルで生きていくことで生じる懸念をいくつか指摘しておきます。
(「叱らない」が子どもを苦しめる)
よく見かける被害者仕草の話題からスタートしていてもはや単なる教育本の範疇を超えていてとても面白かった。
一行目にも書いたけれど,私が昨今気になっていたことと重なることがうまく分析・言語化されていたほか,私には無かった視点の話題もあり,タイヘン勉強になる書籍だった。