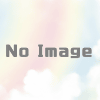【教育】「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化
フィンランドといえば,過去には自立学習が話題になり教育先進国としてよく話題に挙げられてきた。
「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化
デジタル導入の「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化…フィンランド、紙の教科書復活「歓迎」
↑ニュース記事。
デジタルを積極導入した海外の「教育先進国」で、子どもの学力低下や心身の不調が顕在化し、見直しの動きが相次ぐ。
反対に日本は、学校教育の根幹にある教科書を、紙からデジタルに置き換えようと突き進む。文部科学省が主導する推進議論の危うさを指摘する。
人口556万人の北欧フィンランドは、教育を柱とした人材育成に国家の命運を懸けてきた。大学を含む学校の授業料は無料で、小学校以上の教員は修士号を持つ。教育現場へのデジタル導入は早く、1990年代から進められてきた。
2000年に始まった国際学習到達度調査(PISA)で、フィンランドの子どもの読解力は世界一だった。03年に数学的応用力、06年からは科学的応用力もPISAで本格的に測られるようになり、初回は2位と1位。好成績の理由を探る各国の「フィンランド詣で」が続いた。
だが22年には、3分野の順位が14位、20位、9位に落ちた。「教育は、急速なデジタル化に対応できるものではなかった」。アンデルス・アドレルクロイツ教育相(54)は述懐する。
以前のリーヒマキでは、パソコンを使った授業が週に20時間を超えることもあった。「子どもの集中力が低下し、短気になるといったことが、その頃、フィンランド全体で問題化した。デジタルに偏った教育への懸念が高まった」。市のヤリ・ラウスバーラ教育部長(61)は振り返る。
これを読んで『デジタル=悪』といった二元論に持ち込む人も居るかもしれないが……。
こと教育分野ではデジタルを推進しすぎていることや,目的が『デジタル化すること』になってしまっており,『適材適所で使っていくこと』『効果的に用いること』にはなかなかフォーカスされないもの。
デジタルでは,たとえばGoogleMapや地理院地図を用いた地理学習は紙だけではできない調べ方ができるし,ChatGPTの活用による自身の文章校正などもデジタルだからこそできるものでもある。
画面を見ることによる健康被害,集中力の低下(記事では『短気になる』とも)などを考えれば,デジタルのデメリットも目立つ。
逆に,手書きによる記憶の定着など,紙の教材のメリットもある。
デジタルによるコスト削減についても,初期投資のコストは高く,メンテナンスや買い替えも必要な上,適切な管理がなされないことによる不調や故障など,さまざまなデメリットがある。
一度やってみてフィードバックを得るまでは分からないこともたくさんあるので,失敗をおそれず試行錯誤すること自体は大切なのだけれど,まぁどんどん失敗に不寛容な社会になりつつあり,SNSによる私刑に発展するトラブルもよく見かけるもの。
塾では可能な限り対面かつ紙の教材を重視してゆきたいと考えている。