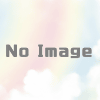【本】習慣と脳の科学
このオッサンいつも脳科学の本読んでんな。
『習慣と脳の科学』
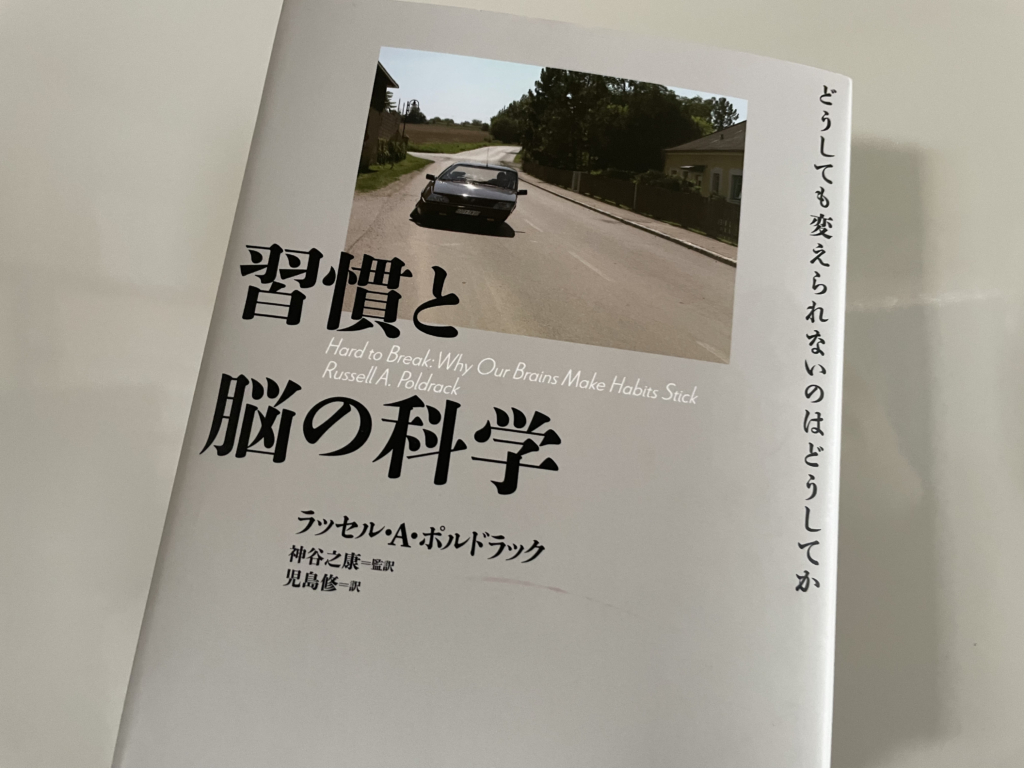
著者はラッセル・A・ポルドラック氏。
副題は『どうしても変えられないのはどうしてか』。
原著は『Hard to Break Why Our Brains Make Habits Stick』。
簡単に述べると,神経科学・心理学・行動経済学など様々な知見から習慣を扱った書。
具体的な実験内容の他,恣意的な結論になっていないか,サンプルサイズがどの程度信頼できるかなど『科学の再現性』も一つのテーマとしつつ,昨今の心理学の在り方にも言及する良書。
もくじは以下のようになっている。
I.習慣の機械 なぜ人は習慣から抜け出せないのか
1.習慣とは何か?
2.脳が習慣を生み出すメカニズム
3.一度習慣化すれば,いつまでも続く
4.「私」を巡る闘い
5.自制心-人間の最大の力
6.依存症 習慣が悪さするとき
II.習慣を変えるには 行動変容の科学
7.新しい行動変容の科学に向けて
8.成功に向けた計画 行動変容がうまくいくための鍵
9.習慣をハックする 行動変容のための新たなツール
10.エピローグ
『習慣とは何か?』を,脳の機能から,心理学の知見から,日常的なできごとから,さまざまな観点から書かれていた。
特に脳科学・神経科学の分野において,どのような実験から何を結論としたのか,どの程度のことが明らかでどの程度のことがまだ不明であるのか,信頼性がどの程度か,……まで書かれていたのがとても良かった。
ニーバーの祈りよろしく『自分に変えられること』『自分に変えられないこと』をしっかり区別することが重要なのは毎度のことで。
『自分の生来の性質』『自分の脳の機能』など,自分のことでも『自分に変えられないこと』はたくさんあるのだと自覚することが大切なのはもちろんで。
『自分に変えられること』のうち,『環境(場・人・コミュニティetc…)を構築する』『場所(住所・生活圏etc…)を変える』『if-thenを組んでおく』『悪い習慣がよみがえりそうな場を避ける』等,そういったことが解決策となってゆくことだろう。
ダニエル・カーネマン先生の『ファスト&スロー』のシステム1/システム2の話題も出てきたほか,モデルベース学習/モデルフリー学習なる概念も新たに知ることができ,タイヘン勉強になった。
アンジェラ・ダックワース先生の名前が挙がったときにはふふっと思わず笑顔になってしまった。
『自制心が人生のあらゆる場面で重要な成果に影響している』という話題からの,『自制心が強いと思われる人は,衝動を抑えるのが得意なのではなく,そもそも自制心を働かせる必要性を回避することが得意であるようだ』という結論,そして『自制心の高い人は(ものごとを)習慣的に行う(=習慣化することで自制心を働かせる必要性を回避し続けている)』『自制心が高いと良い習慣をつくりやすく、結果として努力を伴う自制心を発揮する必要性も減る』……このあたりはかなりの人に響くのではないだろうか。
結局,『習慣化する』→『いちいち自制する必要をなくす』,この流れの重要度が高そうである。
また,お気持ち勢には過剰反応しないでほしいのだけれど,『意志力なるものは存在しない』といった内容も興味深かった。
これはセンセーショナルな文言だけを捉えるのでなく,実際に読んで文脈を捉えてほしいものである。
余談。
これは私個人の最近の体験だが。
少数エピソードによる決めつけが蔓延る場面を見かける/耳にすることが立て続けにあり,今回の書籍のように科学・統計の基本的な考え方が守られているだけでずいぶん心安らぐ読書となった。