【本】単純な脳、複雑な「私」
こいついつも脳科学の本読んでんな。
『単純な脳、複雑な「私」』
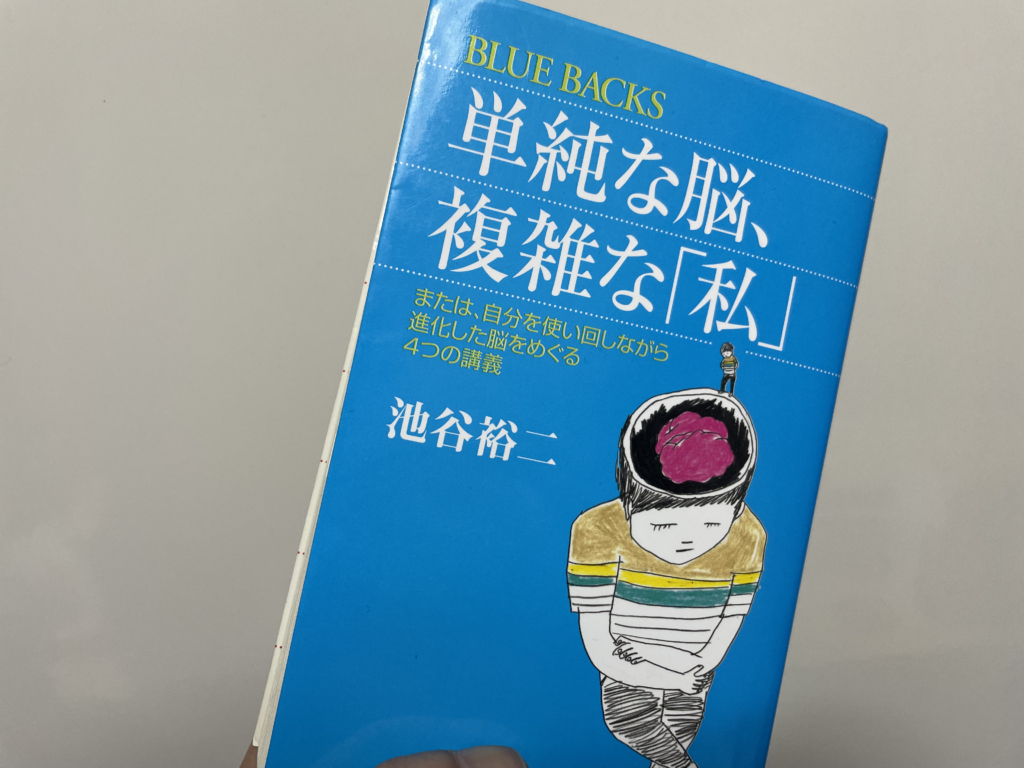
副題は『または、自分を使い回しながら進化した脳をめぐる4つの講義』。
著者は池谷裕二氏。
薬学畑の脳研究者。
昨年発刊された『夢を叶えるために脳はある』を読もうと思っていたのだけれど,これが脳講義の完結編的なものにあたるようで。
前作にあたる表題の書籍が未読であったため,この機会に読むことに。
↓なお,1作目にあたる『進化しすぎた脳』は既読。
1作目を読んだのは4年前のGWだったのか……。
さて。
本書は2013年に出版されたもので,これも10年前の書籍である。
ゆえに,現状の最新の研究結果・解釈とはならないものの,現状へ至る足跡を辿ることにも関心があったので好奇心をもって読み進めることができた。
目次は以下。(各章に33~64の項目がある。)
1.脳は私のことをホントに理解しているのか
2.脳は空から心を眺めている
3.脳はゆらいで自由をつくるあげる
4.脳はノイズから生命を生み出す
副題にあるとおり,このシリーズは中高生への脳講義を文章化したものとなっており,聞き手と対話をしながらの講義を読むかたちとなっている。
ゆえに,中高生が聴いて理解できる話題になっているのが特徴のひとつ。
一気に読み進めたので私の脳内がとっちらかってしまったものの,面白い項目がたくさんあった。
以下,引用は項目名であり,重要なのはその内容であるので,関心のある人は読んでみては。
サブリミナルが教える「やる気」の正体
これはもっと早く読んでおけば良かったなと思わされた項目。
今後の教育にも活かしてゆくことができそう。
もちろん自身のコントロールにも。
ひらめきは寝て待て
睡眠に関わる書籍もいくつか読んできた身として,私は睡眠中の脳の情報整理に絶大な信頼を寄せている。
本書でも扱われていて納得感が増す。
なぜか答えだけわかる
わからないのにできる
理由はわからないけど「これしかない」という確信が生まれる
脳の自動機能と自身の考察とを切り分けて考えたいし,それをメタ認知してゆくことが大切だなと改めて。
お金をたくさんもらうと仕事は楽しくなくなる?
これ,心理学でいう『アンダーマイニング効果』を思い出すなぁと感じたもの。
具体的には,『内発的動機(たとえば「楽しいからやる」「興味があるからやる」)で行っていた活動に対して、外発的報酬(お金・ごほうびなど)を与えると、その活動自体への意欲が低下してしまう,という現象』のこと。
教育現場でよく行われてしまう失敗でもある。
我々大人は子どもたちの内発的動機を削がないようにしておきたいもの。
他人の視点から自分を眺められないと、人間的に成長できない
客観度,メタ認知の程度問題。
完全に他者になることはできないし,俯瞰的に見るにも程度があるものだけれど,どの程度行えるだろうか。
「動かそう」としたときには、脳はもう準備を始めている
これなどは自身だけで確認することは不可能で。
脳の活性化したところを観察して分かることなのだけれど,たとえば『腕を上げよう』と思考するよりも先に『腕を上げるために筋肉を動かす』という準備が始まるほうが早いという。
これは非常に面白かった。
何かをしようとするより先に脳はそれを行う準備を始めているという。
行動の直前の脳の状態が、成否を握っている
「君は30秒後にミスをする」
前著にも同じような話題が書かれていたものだけれど,実際にものごとを行うより前に,脳の状態を観察することでミスするかどうかが分かるという。
脳の状態をモニタリングしながらものごとを行うことで,ミスしないタイミングなどを鍛えられそうなものだけれど,技術の日常運用が待たれる分野である。
(スポーツ競技などの在り方が変わってきそう?)
ほか,項目名ではないけれど,『同時に並行処理できるのは7個まで』という話題も面白かった。
すなわち,日常的に行うものごとを習慣化,システム1として自動的に行えるようにしておくことで,複雑なものごとについても並行処理すべきものの見かけ上の個数を減らすことで,複雑なものごとを単純に行えるようになるのだろうなぁと考えられる。
内容が面白かったので,言及したいことが無限(注:もちろん有限です)に出てきそうなので今日はこのあたりで。
とかく脳は意味のないことを意味づけるのが得意なんだなと思わされるし、それを解明していくことはまだまだ面白そうだなとも思う。




