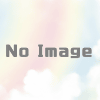【国語】長文が読めない人が増えている理由?
という話題がバズっていた。
長文が読めない人が増えている?
最近、長文が読めない人が増えているのは、単なる集中力不足ではなく、報酬系の依存と神経系のチューニングが短期快楽型に傾きすぎた弊害と言える。長文を読むこと自体が苦痛に変わるだけでなく、そもそも文脈を保持しながら意味を組み立てるという読解力の回路そのものも同じく機能が落ちてしまう。 読解力というのは単に「文字を読む力」ではなく、言葉を文脈の中で解釈し、相手の意図や背景を含めて受け取る力でもあるから、本や文章だけでなく、実際の会話やコミュニケーションにも影響が出る。文脈を保持できないから言葉を断片的にしか理解できず、表面的な意味にしか反応できなかったり、相手のニュアンスを汲み取れずにすれ違いが増えるし、自分自身の思考を整理する力も読解力に依存しているので、理解が浅いと自己言及や内省も曖昧になりやすい。結果として「誤解しやすい」「説明できない」「すぐに反応してしまう」といった形で社会的な摩擦も増える。 自分のことを説明できないというのは単に言葉が出てこないということではなく、自分の内側で起きていることを掴めず整理できない状態そのもので、感じているのに言語化できず、伝えたいのに相手に届かず、結果として誤解されて孤立感が強まってしまうからとても辛い。 説明できるということは内側と外の世界を橋渡しする行為であり、それができないと自己感覚が不安定になってしまうので、自分を説明できる力は安心感や人とのつながりの土台になる。 「自分だけは分かっている」という拠り所があるならまだ人は耐えられるけれど、それすらないと、自分の感じや考えを誰も拾ってくれないどころか、自分自身も拾えないことになる。そうなると、存在の手応えや安心感が一気に揺らぎやすい。
読解力は単なる「言葉の処理能力」と誤解されているけど、背景や文脈を保持するワーキングメモリ、因果関係や全体像をつかむ構造的把握力、行間やトーンを感じ取る感受性といった非言語的な認知リソースに大きく依存していて、実際にはマルチモーダルな認知が働いている。 だから読解力=言語処理力と単純化するのは不十分で、実際には非言語の把握力を土台にしたうえで、最終的に言語に落とし込む力なんですよね。
面白い考察だなぁ。
……という長文が,『長文が読めない人』は読めないという入れ子構造面白いね。
そんな人向けに述べると,『文脈を保持しながら意味を組み立てることを目指そう』くらいになるか。
日々見聞する情報量が多すぎて脳が処理しきれない社会になってきているよなぁというのも最近感じている。
余談。
高市早苗氏の『馬車馬のように働いていただきます』への反応も二極化していましたね。
『(自身と自民党の同志に向けて)馬車馬のように働いていただきます』の意のはずが,『(一般の人たちに)馬車馬のように働いていただきます』と読み取っている人たちもいるそうで。
いやはや。
TVの偏向報道なんとかならんのかねぇ。
『動画を見たらAIと思え』とでもいえるような世の中になってきてはいるものの,今回は生放送で視聴していた人も多かったようで。
webも局所的には偏りがあるし,エコーチェンバーには要注意だけれど,自身で情報の比較をできる分まだマシか。