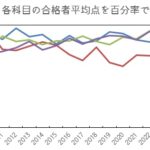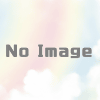【AI】AIを引っ提げてやってきた大学院生
……という記事が話題に。
AIを引っ提げてやってきた大学院生
↑元記事。URLの通り,東京大学の学内広報。
驚かされたのは、彼が経済学を専攻する学生ではなく、それどころか経済学をこれまでほとんど学んだことがないという点です。彼の関心は技術の新領域への応用、特に「生成AIの新活用」にあり、専門外である経済学という分野で、AIとの対話だけでどこまでのレベルの研究ができるかを1年間かけて試してみたというのです。研究のアイデア出し、先行研究のレビュー、理論モデルと仮説の構築、データの探索と収集、計量ソフトを用いた分析、図表の作成、英語論文化に至るまで、さまざまなAIツールを組み合わせながら、ほぼ独学で試しているとのことでした。
AIとの対話と考察,ほぼ独学で。
専門学術誌に挑戦できる水準に達してしまったという。
私も日常での考察にAIを活用する場面は増えてきていて,以下のことはかなり実感している。
AIと対話し,AIの出力したものを評価する目,AIに適切な問いを投げかける力───。
これさえあれば,実験を経る必要のない分野───(失礼にあたることは重々承知であるけれど,)哲学やこのたび話題となっている経済学など───では,独学でものごとを築き上げてゆくことが,従来よりずいぶん取り掛かりやすくなっているのではないか。
そう感じる。
AIを活用できる視座に立てれば,どんどん世の中が楽しくなってゆくことだろう。
反面,AIに淘汰されるのを待つような状況も同時に生み出されている。
いま,まさにChatGPTをはじめ,Gemini,Claude……さまざまな生成AIが台頭している。
この記事を書いている現在は,Nano Bananaが話題だけれど,1年といわず1ヶ月後にはまた別のAIが席巻しているのかなぁ。