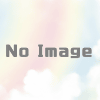【AI】慶應大のAI対策トラップが面白い
AIに振り回される側,AIをツールのひとつとして使う側,分かれてゆく世の中。
慶應大のAI対策トラップが面白い
このPostを見ていても,感じること・考察することが人それぞれに分かれそうな話題ではあるけれど。
私個人としては,『AIはOK』『AIはNG』といった極論ではなく,どのように使っているか・あるいはどのように評価しているか……という目で見ておきたいもの。
自身の考察とAIの出力を比較検討し,ブラッシュアップに用いる……そして,AI特有の間違い方などに気付いて修正していく……といったことを恒に行ってゆく側であれば,どんどん用いてゆくのはアリであるように思う。
私自身も日常的に使うようになってきた。
自身の不得意な分野では鵜呑みにすることによる失敗は数知れず,そしてweb上にはあまり出回らないローカル事情のザツさなど,AIであるがゆえの過ちは多くの方々が見てきたのではないかなぁ。
他責性の強い人にとっては『(自分ではなく)AIが言っていたから』という大義名分を作りやすい存在として認識してゆく可能性も考えられ,それはイヤな世の中だなぁとも思う。
話はそれるが,以下のPostがバズっており,人によって見解が割れていたのも面白い。
レポートの提出が遅れた学生からのお詫びのメールが、AIで生成された疑いがあるとの同僚からの報告に、いよいよ来るところまで来たという感じが否めない。
どういったふるまいが正解とされるかは位相によって異なる。
その位相に長期間馴染んだ人であれば主観的な評価とその位相の社会的な評価が一致してくるものであるが,新人にとってはそうではない。
面白いのは,話の主旨が,AI生成による謝罪自体と謝罪文のAI生成疑いが始まる世の中になったことのどちらを指しているのだろう……という読み取りが分かれるところ。
謝罪文については,いくら当人に謝罪の気持ちがあろうと,謝罪相手の文化的背景によって何が誠意にあたるかが違うし,地雷を踏まぬようAIに添削を任せるのは正解のように思う。
ただ,相手からのAI疑いが発生したことにより,相手の思う誠意に応えられておらず,結局謝罪に失敗しているように見える。
それを鑑みると,今回の件についてはAIを使う側が使い方を間違えているか。