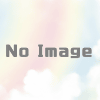【本】氏名の史実・現実
このオッサンいつも笹原先生の本読んでんな。
『氏名の史実・現実』
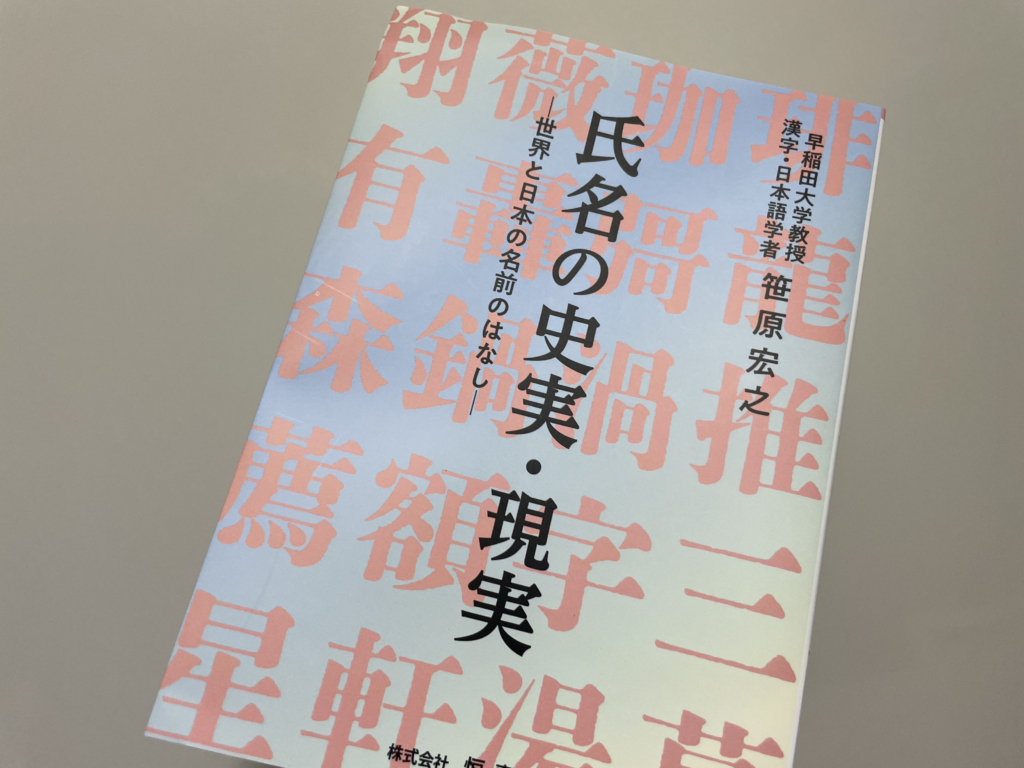
著者は笹原宏之氏。
副題は『世界と日本の名前のはなし』。
笹原先生についてはこのブログで何度も登場しているのでもはや必要ないかもしれないが,以下。
↑早稲田大学研究者データベース。
↑wikipedia(wikipediaは単なる憶測やウソが書かれていることも少なくないので注意。)
簡単に述べると,『日本の漢字に世界でいちばん詳しい人』という紹介になるか。
今年度の三省堂の教科書,中学1年国語にも登場しているとか……?(表紙がペンギンのもの?)
目次は以下。
第一章 日本の姓と名の漢字
第一節 日本の姓名と漢字
第二節 多い氏、画数の多い氏、長い氏名など
第三節 国字・造字
第四節 異体字
第五節 誤った届・受理・処理
第六節 潜在的な要求
第七節 命名の傾向
第八節 小結
第二章 各国の名字・名前と文字
第一節 世界の名字事情
第二節 漢字圏の名字事情 中国と台湾の文字
第三節 漢字圏の名字事情 韓国とベトナムの姓
第四節 ローマ字圏の名前
第五節 漢字圏の名前
第六節 日本に多い名字とは?
第七節 名字ランキングを作った人
第八節 鈴木か、佐藤か
第九節 民間の名字ランキング
第十節 日本の名字と名前
第三章 日本の姓名にまつわる伝説と検証
第一節 「上沼田下沼田沼田」という名字は実在したか
第二節 「雲」三つと「龍」三つからなる八十四画の「たいと」という氏は実在したか
第三節 「龍」四つからなる六十四画の漢字「てつ」を用いた名は実在したか
第四節 「神」と書いて「アホ」と読ませる氏と名は実在したか?
内容は書籍自身と目次が表している通り。
目次を見ただけでも『苗字』でなく『名字』と表記しておられることに気が付くもの。
この疑問も書籍の中で解説されていて助かった。
以下,私の感想。
・リテラシーと探究と調査
日本における漢字や姓名にかかわるものごと……。
ネット社会であらゆるものを即座に調べられるようになってなお,憶測・決めつけ・思い込み・知ったかぶりが事実のように述べられている場は多々あり,これらの区別の難しさ・情報リテラシーの大切さを実感できる書籍。
口承であれ文字伝承であれ,悪意があれ勘違いであれ,解釈違いであれ,面白おかしく尾ひれを付けてしまったのであれ,伝言ゲームを繰り返すとこうなってしまうのだという実例が紹介されているのがいつも面白い。
また,それを『ホントに?』『情報ソースは?』と疑いの目を向け,あらゆる手段を用いてご自身の足で調査してゆく先生の行動力は圧巻。
『疑いの目を向けること』をネガティブに捉えられる場は枚挙にいとまがないが,新たな発見や一次情報に近いものを探す上で欠かせないものである。
研究の紹介というものは,その研究の『目を引く結果』『もてはやされそうなもの』だけが紹介され,面白おかしくされがちなもの。
これは多数の人に認知してもらうという利点もある反面,面白ければいい・満足できればいいと間違った状態で伝わったり単に消費されるだけにもなりがち。
こういったものごとが繁茂する中,研究における泥臭い部分に詳しく触れられ,それを筆者の視点で辿れるのがとてもありがたい。
・データの扱いと評価
名字ランキングの項で詳しく述べられていたもの。
存在しているランキングデータの信頼性・妥当性について,どのような調査方法が用いられており,どのような計算がなされているか……こういったところまで辿ることの大切さが分かる。
名字にあたっては,以下のようなものを同一のものと集計とするか否か。
『漢字は異なるが同じ読みのもの(中村(ナカムラ)と仲村(ナカムラ)など)』
『読みは異なるが同じ漢字のもの(門田(カドタ)と門田(モンデン)など)』
『異体字がいくつかあるもの(渡邊と渡邉など)』
……など,集計の出発点でさえこんなに多種多様なのだと思わされる。
私の名字は『髙橋』でなく『高橋』なのだけれど,これも集計の仕方によって順位が大きく変わりそう。
(よく間違えられますが,相手から確認されたときや儀礼的な場を除き,特に指摘しません。)
髙橋/高橋はさすがに同一のものと数えるのが標準になりそう。
書籍を読む限りは,概ね読みをベースに集計されてきたような印象。
・苦言
実は、日本では、政府が名字の統計を取ったことは一度もない。
個人や民間でなく国の公式資料としてあっても良さそうなのになという思いは私もある。
活用の仕方も種々ありそう。
筆者も解説を頼まれることがあるが、テレビ制作者は説明の意図をきちんと理解しようとしない傾向があるため、よく番組などを選ぶようにしており、最近はあまり引き受けなくなった
マスコミの,報道したいものを報道したいように報道する面はweb上でもよく見かける。
すべてがすべてというわけではないのだけれど。
善意を踏みにじられたとて,踏みにじられた個人の抗議よりTVの影響力のほうがバツグンであり,個人にとっても社会にとってもマイナスで終わることも珍しくない。
ちょうどTV番組『月曜から夜ふかし』において以下の騒動・謝罪文があったことが記憶に新しい。
放送では「あんまり中国にカラス飛んでるのがいないですね」という話の後、「みんな食べてるから少ないです」「とにかく煮込んで食べて終わり」といった女性の発言がありましたが、実際には女性が「中国ではカラスを食べる」という趣旨の発言をした事実は一切なく、別の話題について話した内容を制作スタッフが意図的に編集し、女性の発言の趣旨とは全く異なる内容になっていました。
(注:現在はさらに書き替えられている。)
私はTV番組については大学生の頃から観なくなった。
観るのはピンポイントで観たい番組があったときのみで,年に10本もいかないだろう。
・想起
地域により名字に偏りがあるといった話題の項では,『そういえば因島は「岡野」だらけだと聞いたことがあるなぁ』と思い出したり。
大学在籍時に英語担当教員ハラランポス・カルパキディス先生から『原蘭干』という印鑑を見せていただいたことを思い出したり。
と,いろいろ書いていると収拾がつかなくなりそうなので今日はこのあたりで。