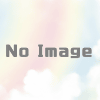【教育】対話について思うこと
会話が成り立たない論?
対話について思うこと
先日の交流会において,言語が通じなくても対話は可能であると実感する機会がたくさん得られた。
対話ができること自身が喜びだなと,改めて感じる。
子どもの親であれば,赤ちゃんだった子どもが喋るようになったこと,話が通じるようになったこと,伝わらなくてもどかしい思いをしたこと,さまざま体験してきたことだろう。
私は,多くの人と交流する機会があると,『対話とは何か』を振り返って考察することが頻繁にある。
対話相手の人格がどうこうではなく,『対話』という概念自体が何かという考察であり,糾弾するのが目的ではないことに注意されたい。
とある講演会の中で,以下のようなやり取りがあった。
講演者『日本人からは魚・醤油のにおいがするらしいですね』
講演者は軽いノリで述べたようであったが……。
私『それ,韓国人からキムチのにおいがするって言ってるようなものでは……』
と,こうつぶやいた。
すると,
隣の人『そんなこと言ったら殺されますよ!?』
と,こう返ってきたのだ。
このやり取りは周囲の人にどう受け取られただろうか。
私は『Aという表現はBという表現くらい差別的な含意があるととられるのでは』という意見であり,AもBも肯定しておらず,同型である旨を述べている。
『気付いていないかもしれないが,講演者の発言はそれくらい危険な表現なのでは?』という旨を伝えたかったのだけれど,それが伝わっていないことがよく分かる返答である。
一方,隣の人は『危険な表現を発言すべきでない』という旨を述べている。
この記事の読者の皆さまはどう読み取っておられるだろうか。
こういったやり取りの難しい点は,この件から明らかに対話のレイヤーがズレているにもかかわらず,これをいちいち指摘する必要もなければ,指摘したところで伝わらない可能性があるところ。
大局的な話題が主旨であるのに,途中に出てきた具体例が主旨だと思い込む傾向のある人,こういった人である可能性が浮上してしまう。
同じ母語で対話をしているのだけれど,意図は通じない。
これを体感する機会にもなってしまった。
対話のレイヤー差が大きいと,幼い子の親のように,介助者・被介助者の関係になりかねず,1対1であれば共依存的な関係に発展する危険性すらあるから,このあたりの扱いは難しい。
ものごとをどの程度メタ的に考察できるか,メタ認知できるかには個人差があるけれど,それでも心的・知的に互いに寄り添おうとする意思があれば対話はスムーズだし,豊かなものになる。
反面,分かっているつもり,相手側に問題があると互いに思い込んでおれば,経験や知識が豊かであろうとも,対話は難しくなるだろう。
世の中には知らないこと,なかなか認知できないことがあまりに多い。
私もちょっとしたことで傲慢にならぬよう,謙虚さを常に意識してゆきたい。
(ちょっとした対話でこんなことをついつい考察してしまうオッサンです。)
余談。
現代数学の圏論に関する書籍を読んでいるのだけれど,ものごとを抽象的に考え,かつ言語化してゆくのに日常使いできそうな内容で,ひさびさに数学を学ぶ感じもしてとても面白い。
読み終わったらオススメ本になりそう。